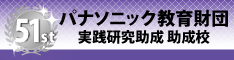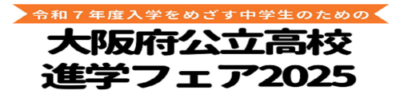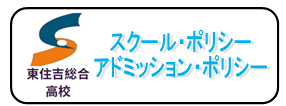第1 学校教育活動の方針
(1) 学習指導の方針
・工業・商業を学べる総合学科として多様な進路実現を可能にし、生徒が夢を実現できる学校をめざし、魅力的なカリキュラムを編成する。
・ビジネス系列の中心的科目である「ホスピタリティ」をより実践的なものへ発展させる。
・年2回、授業アンケートを実施し、生徒の意見を反映する。
・「産業社会と人間」、「総合的な探究の時間」や特別活動の中に「志学」を取り込むとともに、キャリア教育の充実に努める。
・工業の系列においては、工業技術に関する基礎的、基本的な知識技能の習得に努める。
・ビジネス系列においては、商業に関する基礎的、基本的な知識技能の習得をめざし、魅力あるカリキュラム編成や施設設備を整備する。
・各種資格取得に係る支援を行うことで、生徒の自己実現への一助とする。
各教科の目標
ア 国語科
論説文や文学教材をとおして、言語文化に対する関心を高め、言語感覚を磨きながら、理解や共感を深める。また、前述の学習の過程で身につけた国語力を駆使して、自己の考えや思いを状況に応じて適切に表現できるようにする。
イ 地歴・公民科
社会の一員として基本的知識と社会性を身につけた人格の成長を促す。同時に社会の諸問題に関心を向け、科学的精神と公正な判断力をもった社会人の育成をめざす。
ウ 数学科
基礎的事項の徹底をはかり、数学に対する基本的・効果的な学習態度および事象を数学的に考察し、処理する能力を養う。
エ 理科
生活に関係の深い事象や実験・観察を通して自然への関心を高め、基礎的な原理や法則を理解し、総合的考察能力および創造的能力を育てることを目標とする。
オ 保健体育科
実践の集団の中での自己の役割を自覚する。また、安全・公正な態度を育成し、生涯をとおして、スポーツに親しむ必要性を認識する。
カ 芸術科
芸術の幅広い活動をとおして、創造する楽しさを経験させ、自発的な想像力や感性を育てる。
キ 英語科
英語をとおして、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図る態度を育てる。また、「聞く・話す・読む・書く」などのコミュニケーション能力を養う。
ク 家庭科
家族や家庭の意義、男女が協力して家庭経営や保育を行うことの大切さを理解させ、生活に必要な知識・技能を習得する。
ケ 情報科
1年次で基礎的なメディアリテラシーを学び、2・3年次の選択科目で応用能力を身につける。
コ 工業科
日本の工業力の維持・発展に寄与するエンジニアの育成を目的とする。また、基礎的な知識・技能・態度を習得し、工業人として正しい自覚をもつ。
サ 商業科
商業の基本的な知識や技能を身につける。社会人としてのマナーや資質を育み、変化し続けるビジネスの世界で生涯をとおして、学び続ける姿勢を涵養する。
シ 総合科
「産業社会と人間」の授業をとおして、自己の将来の進路について見定め、希望する進路実現のために必要な科目選択を行うとともに、豊かな高校生活を送る態度を育てる。
(2) 特別活動の方針
・修学旅行等の自然体験を位置付け体験活動をとおして、生徒の人間としてのあり方や生き方の自覚が深められるようにする。
・生徒会活動や部活動を活性化し、集団としての規律、連帯感、協同の精神などを涵養する。
・行事等のクラス活動を通して社会性の育成を図る。
(3) 道徳教育および生徒指導の方針
・道徳教育については道徳教育推進教員を中心に全教員が協力して行い、人間としてのあり方や生き方についての考えを深めるように指導する。
・すべての生徒が健全な人格の発達をめざすため、高校生活をとおして、将来の目標をもち、自律精神を確立するよう指導する。
・基本的生活習慣の重要性を理解させ、規律ある学校生活を送るよう指導する。
・地域の人材を活用した図書ボランティアや公立図書館との連携等による読書活動の推進を図り、「生きる力」を育む。
・あらゆる教育活動をとおして、基本的な生活習慣と規範意識の醸成に努めるとともに、問題行動を未然に防止するため、教育相談の充実を図り、関係機関との連携に努める。
(4) 進路指導の方針
・生徒が将来の生き方への関心を深め、自分の能力・適性を発見できるようなカウンセリング機能の充実に努めるとともに、進路に関する適切な情報を提供するなど、ガイダンス機能の充実を図る。
・生徒の自己理解を助成するとともに個性の伸長を図る。
・生徒が自己の資質・能力・適性に応じて自主的に進路を選択し、将来の生活において自己を実現する能力を育てる。
(5) 人権尊重の教育の方針
・人権教育に係る国および府の関係法令等に基づき、人権三法や府人権三条例が成立したことも踏まえ、あらゆる教育活動において人権教育を計画的・総合的に推進する。
・人権および人権問題に関する正しい理解を深め、女性、子ども、障がい者、同和問題(部落差別)、在日外国人、性的マイノリティ等に係る人権問題をはじめ、様々な人権問題の解決をめざした教育を人権教育として総合的に推進する。また、人権教育の推進については「大阪府人権施策推進基本方針」、「大阪府人権教育推進計画」等の方針、計画等に留意する。
・すべての教職員が研修等をとおして、自らの人権感覚を高めるとともに、あらゆる場面で人権意識を絶えず見つめ直しつつ教育活動を行い、校内組織体制を整備する。
(6) 生徒の安全・安心の確保、健康管理と指導の方針
・AEDの使用を含めた心肺蘇生法を実施できる体制を整え講習等を毎年行う。講習等では「死線期呼吸」についても周知する。
・喫煙・飲酒・覚せい剤・大麻等薬物乱用防止教育について、指導計画を立てるとともに関係機関と連携しながら、学校教育活動全体をとおして取り組む。
・健康観察や全教職員での健康指導、保健指導の徹底により、インフルエンザ等の感染症や食中毒の罹患を防ぐとともに、早期発見に努める。
・学校施設・設備の安全点検を励行し、災害防止に努めるとともに、必要に応じ学校保健・安全委員会を開催してすべての教育活動を通じて安全指導の徹底を図る。
・自然災害等に備えた防犯および防災計画を策定する。
・AED講習、食物アレルギー(エピペン含む)研修を充実する。
(7) 学校運営の方針
・「よりよい社会を切り拓いていく人間」をめざし、SDGs(持続可能な開発目標)の視点も踏まえ、多様な価値観を持つ他者と調整しながら物事を前に進める力(他者共有力)を育成する。
・地域との連携を密にし、心豊かな人材を育成する。
・多様な進路希望に対応して、よりきめ細やかな進路指導に努める。
・本校の特色ある教育体制の広報に努め、入学希望者の増加をめざす。
・情報の入力(読む、聞く)、処理(まとめる:情報の処理、関連づけ、課題発見、課題解決策の提示等)、出力(書く、話す)能力を育成するため、探究活動の推進をはかる。
・1人1台端末、オンライン授業を視野に入れたICT等を活用した取組みを推進する。
(8) 教員の研修方針・研修計画
・「大阪府教員等研修計画」を活用し、あらゆる機会において教職員に求められる基礎的素養である人権感覚や人権意識の育成に努める。
・生徒指導、授業づくりなど校外の研修で得たことを校内で実践する。また、OJTの推進に努め、教職経験年が少ない教職員の育成を心がける。
・統合ICTを活用した校務のICT化を進めるとともに、研修の充実を図る。
・生徒の個人情報の保護、体罰防止、セクシャルハラスメントの防止、いじめ対応等の緊急の課題についての理解を深め、校内組織を活用して迅速かつ適切に対応できるように努める。
・大阪府教育センターや各種研究団体の主催する研修会への積極的な参加を奨励し、所属する分掌での研修報告を実施して互いの研修に資する。